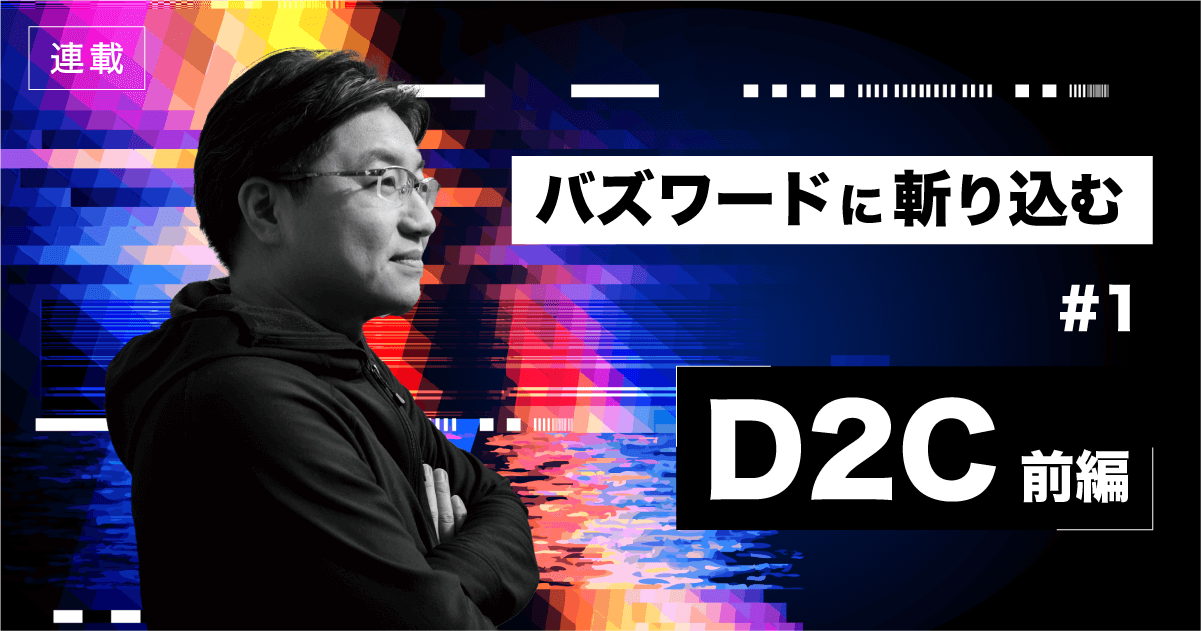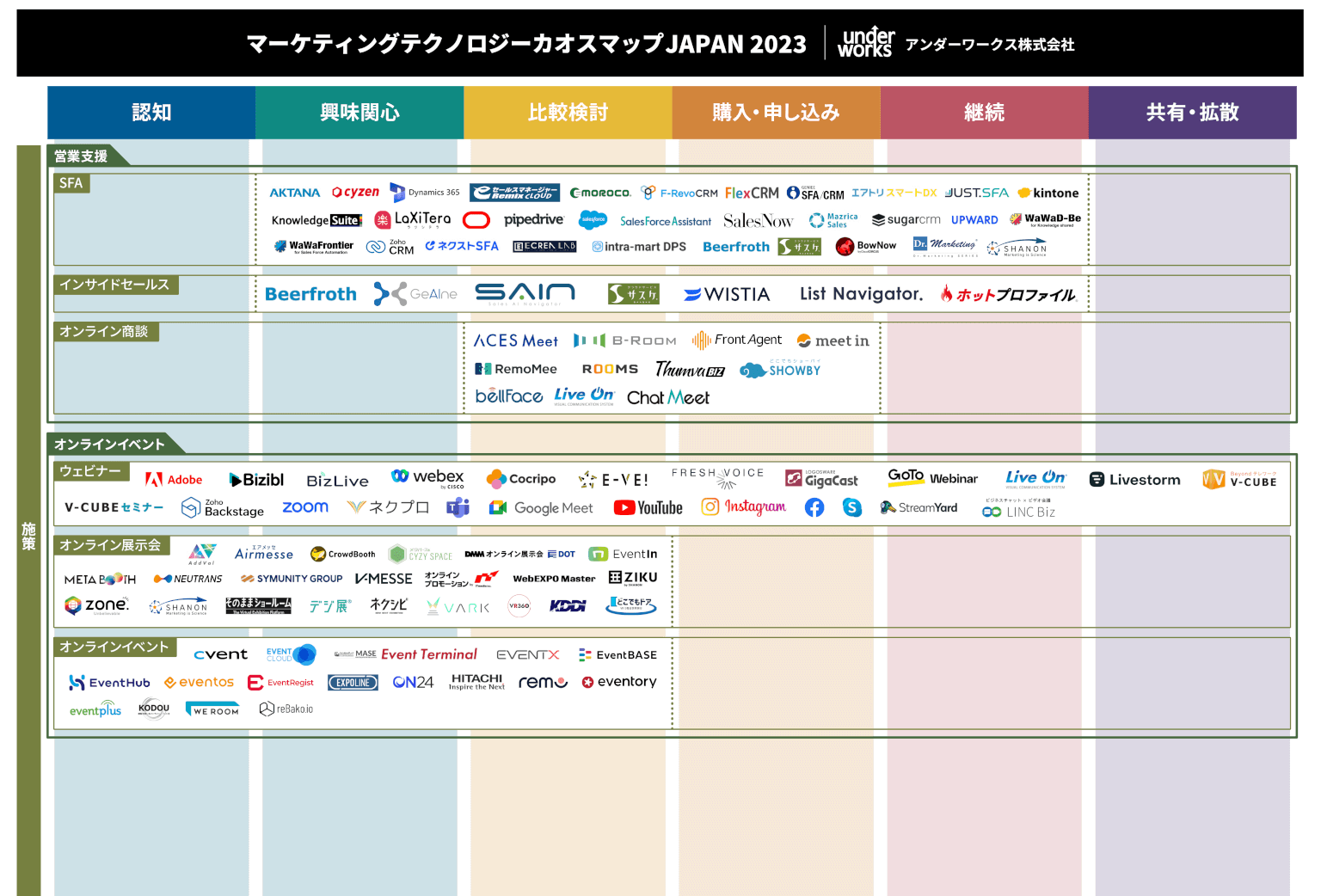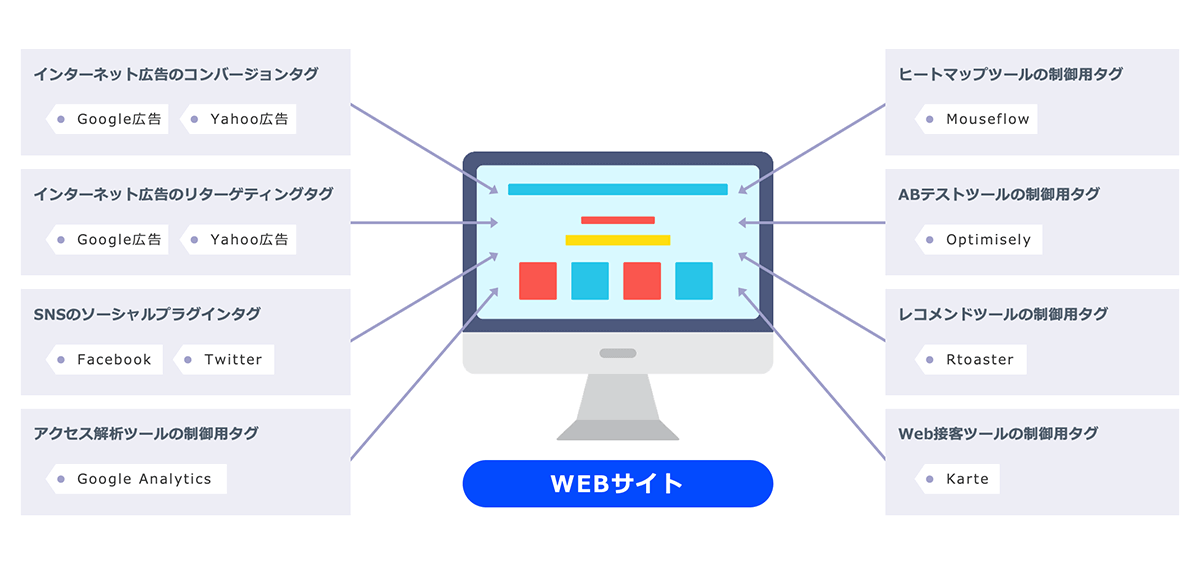目まぐるしいスピード感でトレンドが生まれ変わるデジタルマーケティング業界。そのトレンドの時流をもっとも意識するのは「バズワード」を目にした時かもしれません。ここで言うバズワードとは、特定の期間に、多くのメディアやビジネスパーソンの間で非常に頻繁に使われる、トレンドを端的に表現する単語を指します。
最近では「DX」や「サブスク」など、さまざまなキーワードがバズワードになっていますが、日常的に耳にするこれらの言葉は、意外と定義があいまいなままになっていたり、本質的な意味が見過ごされているのではないでしょうか。
そんなバズワードをひとつずつ取り上げ、本質的な意味を見極めていくのが本連載です。第一回目で取り上げるバズワードは「D2C」。本記事では、形骸化しつつある「D2C」という言葉の本質を解き明かし、それに取り組むために必要な一歩について、アンダーワークス代表取締役の田島が解説します。
(スピーカー=田島学、取材・文=宿木雪樹、編集=DMJ編集部)
D2Cは30年前からあった?インターネットと直販モデルの歴史
D2C(Direct to Consumer)は、文字通りの意味としては、中間流通業者を通さずに自社製品を顧客に直接販売することを意味する言葉です。
昨今のDXブームと相まってバズワード化しているD2Cですが、その言葉の本質を理解するために、インターネットと販売手法の歴史を少し前から振り返って考えてみます。
1990年代後半、いわばインターネットが民主化されはじめた時代には、メーカーが消費者に直接販売するモデルはすでに大きな注目を浴びており、直販に取り組む企業も増加していました。
たとえば、パソコン販売会社のDellは、BTO(Build To Order)という販売戦略を主軸に、インターネット経由で顧客がカスタマイズしたパソコンの販売を開始し、大きく成長しました。現在では当たり前とされる自分が欲しいスペックを選んで注文するモデルの先駆けと言えるでしょう。パナソニックや当時のソニーなど国内のパソコンメーカーが自社のWebサイトで直販サイトを立ち上げ始めたのも2000年頃です。
2000年代前半には、SPA(Specialty store retailer of Private label Apparel)というキーワードとともに、企画・生産・販売を一体化した事業が注目を集めます。アパレルメーカーのユニクロやGAP、デバイスメーカーのAppleなどが代表例とされますが、こうしたSPAもD2Cとは切り離せない概念だと考えられます。
このような歴史を振り返ると、企業がインターネットを通じて直接的に消費者に商品を売るというモデルそのものは30年前から存在していたことがわかります。そう考えると、現在注目されているD2Cという概念を、単に消費者への直販モデルと捉えるだけでは少し物足りない気がしてきます。
D2Cという概念が登場する背景となった4つの環境変化
それでは、流通業者を介さず消費者に直接販売する「直販」と「D2C」は、一体何が異なるのでしょうか。次の環境要因からヒントを見出してみます。
1. ソーシャルメディアや口コミサイトの普及
2000年代後半からソーシャルメディア(Twitter、Facebookなど)が普及したことは、消費者の購買行動と企業のマーケティング活動に大きな影響をもたらしました。ユーザーはインターネットを情報収集の窓口のみならず、双方向のコミュニケーションの場として活用するようになりました。「Web2.0」といった言葉もバズワード化し、「価格.com」などの口コミサイトも普及しました。
2. 海外工場での商品生産、グローバルサプライチェーンの一般化
近年、多くの企業が中国や東南アジア、インドなどの工場に商品生産を委託することが当たり前に行われるようになりました。中国やベトナムの経済の開放やインドでのITの発展など、小ロットでの格安グローバル生産を前提としたサプライチェーン体制の構築が一般化してきました。グローバル化の進展により、大きな資本がなくても格安の生産体制をつくれる時代になったと言えるでしょう。
3. メイカーズムーブメントの到来
2010年代に入ると「メイカーズムーブメント」と言われる、デジタルツールを活用して個人がプロダクト生産に携わり、事業化する潮流が注目され始めました。3Dプリンタに設計図を流し込むことで誰もがモノをつくり、販売できる時代の到来。これは「第三の産業革命」とも呼ばれ、商品販売に関わるステークホルダーに大きな衝撃を与えています。このメイカーズムーブメントは、KickstarterやMakuakeなどの「クラウドファンディング」や、「CtoC」といった新たな潮流を生み出すことにも繋がっています。
4. デジタルネイティブなZ世代の消費マーケットの拡大
最後に、生まれながらのデジタルネイティブとして注目されているZ世代の価値観について触れます。Z世代とは1990年代半ばから2012年頃に生まれた世代を指す言葉で、これまでの世代とは異なった購買行動への価値観を持っていると言われています。Z世代は、物心がつく頃からインターネットやデジタルツールに触れており、TwitterやInstagramなどで物理的な距離と関係なく世界中の個人と直接情報を交換するなど、マスメディアや大手企業といったフィルターを介さず社会を認識する世代です。
したがって環境や社会課題に敏感であり、その価値観は購買行動にも如実に反映されているとも言われています。また、物理的なモノ以上に、その裏側にあるストーリーを認知し、関心をもち、購入するまでの体験に重きを置くとも言われています。いわゆる「シェアリングエコノミー」や「所有から利用」などのコンセプトを、金銭的な損得に限らない感覚で強く持っていると考えられます。
以上のような、グローバリズム、ものづくりへの投資ハードルの低下、ソーシャルメディア(インターネットのインタラクティブ性)が、生まれながら、もしくは幼少期から存在していたZ世代の価値観形成に影響し、新たな商品販売のあり方として注目されるようになったのがD2Cである。そういった捉え方ができるのではないでしょうか。
D2Cにいち早く取り組んだのは海外スタートアップ
アイウェア事業のWarby Parker(ワービーパーカー)
D2Cの時流をいち早く捉えたのが、2010年後半頃の米国のスタートアップ企業です。まずは、D2Cの先駆者として有名なアイウェア販売のWarby Parker(ワービーパーカー)を例に挙げてみましょう。
Warby Parkerは、米・ニューヨークで2010年に設立され、スタイリッシュなメガネを適切な価格で販売するアイウェア事業を展開しています。当初はオンライン販売のみを行い、30代以下の顧客の6割以上がSNSで認知し購買したと言われています。
販売個数に応じて、非営利団体への寄付や、発展途上国でのメガネ産業従事者向けのトレーニングなどを実施し、いわゆるソーシャルグッドに向けた取り組みを明確に打ち出しました。また、デザインはイタリアで、フレーム加工は中国で行うといった複雑なメガネ生産を垂直統合することで、コストメリットを出したと言われています。
こうして、Warby ParkerはD2C初のユニコーン企業(未上場で1000億円以上の価値のある企業)として名を馳せた後、2021年秋にはニューヨーク証券取引所に上場し、売上高400億円以上、時価総額7000億円以上を誇っています。
アパレル事業のBonobos(ボノボス)
次に、Bonobos(ボノボス)の例を見てみましょう。Bonobosは2007年に米国で創業されたアパレル製造販売のスタートアップで、創業者のAndy Dunn(アンディ・ダン)氏は、自社の業態を、Digital Native Vertical Brand(DNVB)と呼んでいました。商品の企画から製造、販売、顧客サービスまでを垂直且つデジタルで行うという意味です。前述のSPAをデジタルネイティブなブランドで体現するイメージに近いでしょうか。
Bonobosは顧客サービスに力を入れており、「Bonobs Guideshop」と呼ばれる試着に特化したコンセプトショップを実店舗として立ち上げ、予約客が専門的なカスタマーサービスを受けられる仕組みを作りました。これにより、店舗での試着体験が好評となりECでの売上が伸びるビジネスモデルとして有名になりました。
その後、2017年にBonobosはリテール大手のWalmart(ウォルマート)に買収されますが、販売拡大への課題はSNSの活用が上手くいかなかったからという声があります。製造と直販体制、実店舗での成功をもってしても、SNSを上手に活用しなければD2Cでの成功は難しいことがわかる事例とも言われています。
以上に挙げたWarby ParkerやBonobosのようなD2Cモデルの成功に倣い、今では多くのスタートアップがD2Cの手法で事業を展開しています。このような歴史の流れや背景、米国でのD2Cブランド、スタートアップ勃興の流れを踏まえ、後編では、D2Cの本質的な意味と大手企業への波及、日本企業への示唆などを考えてみたいと思います。