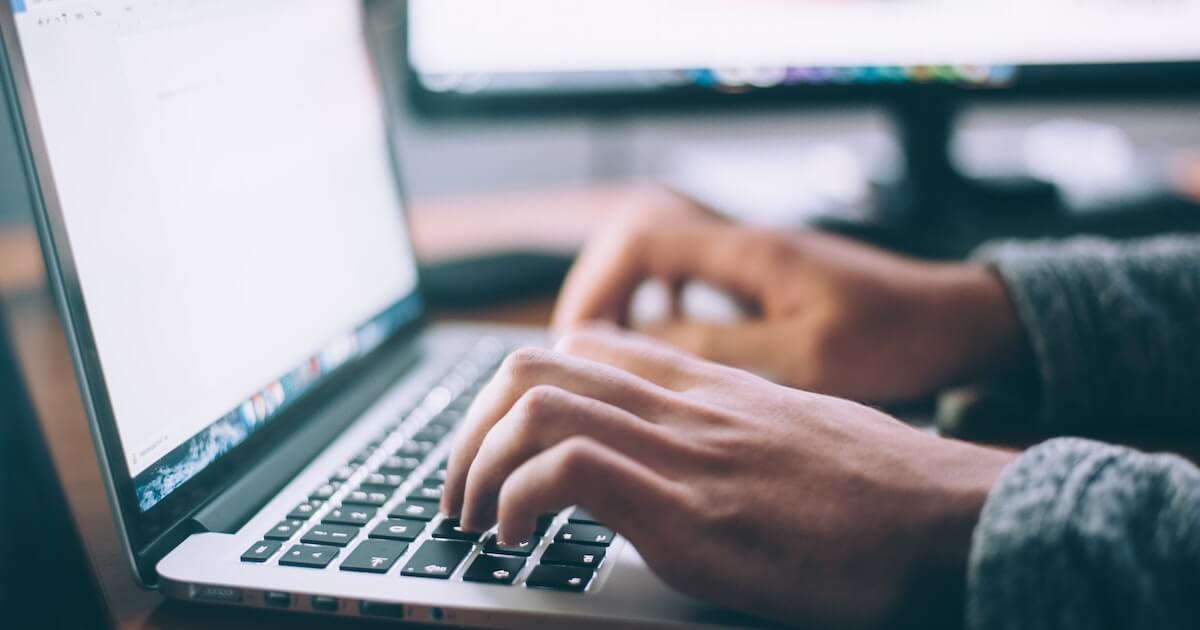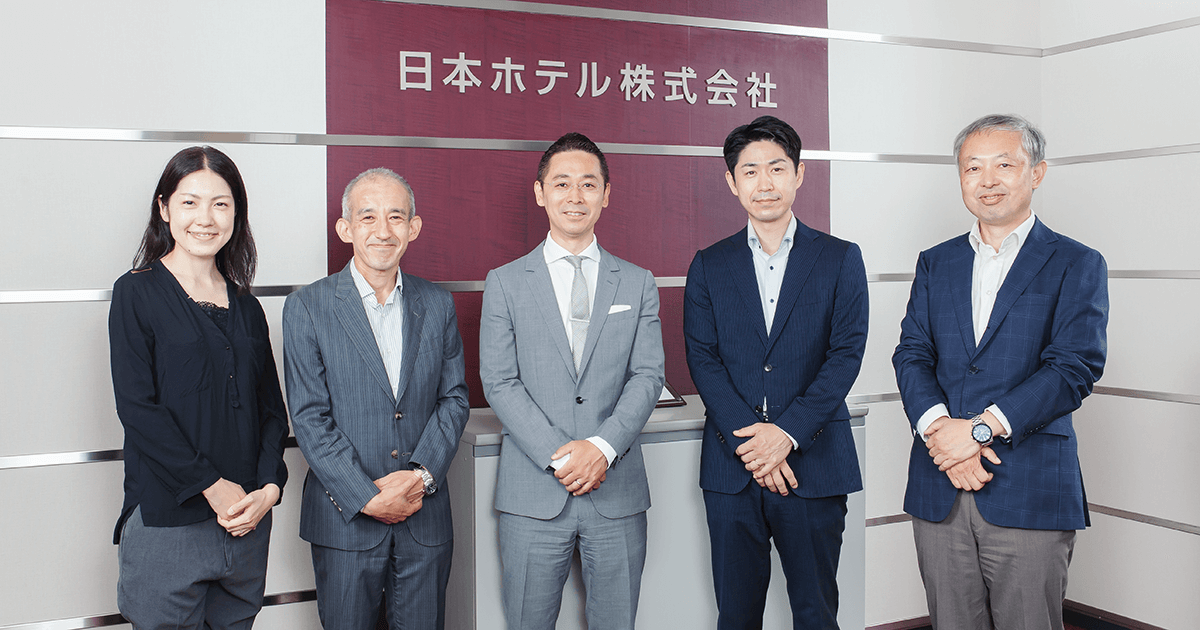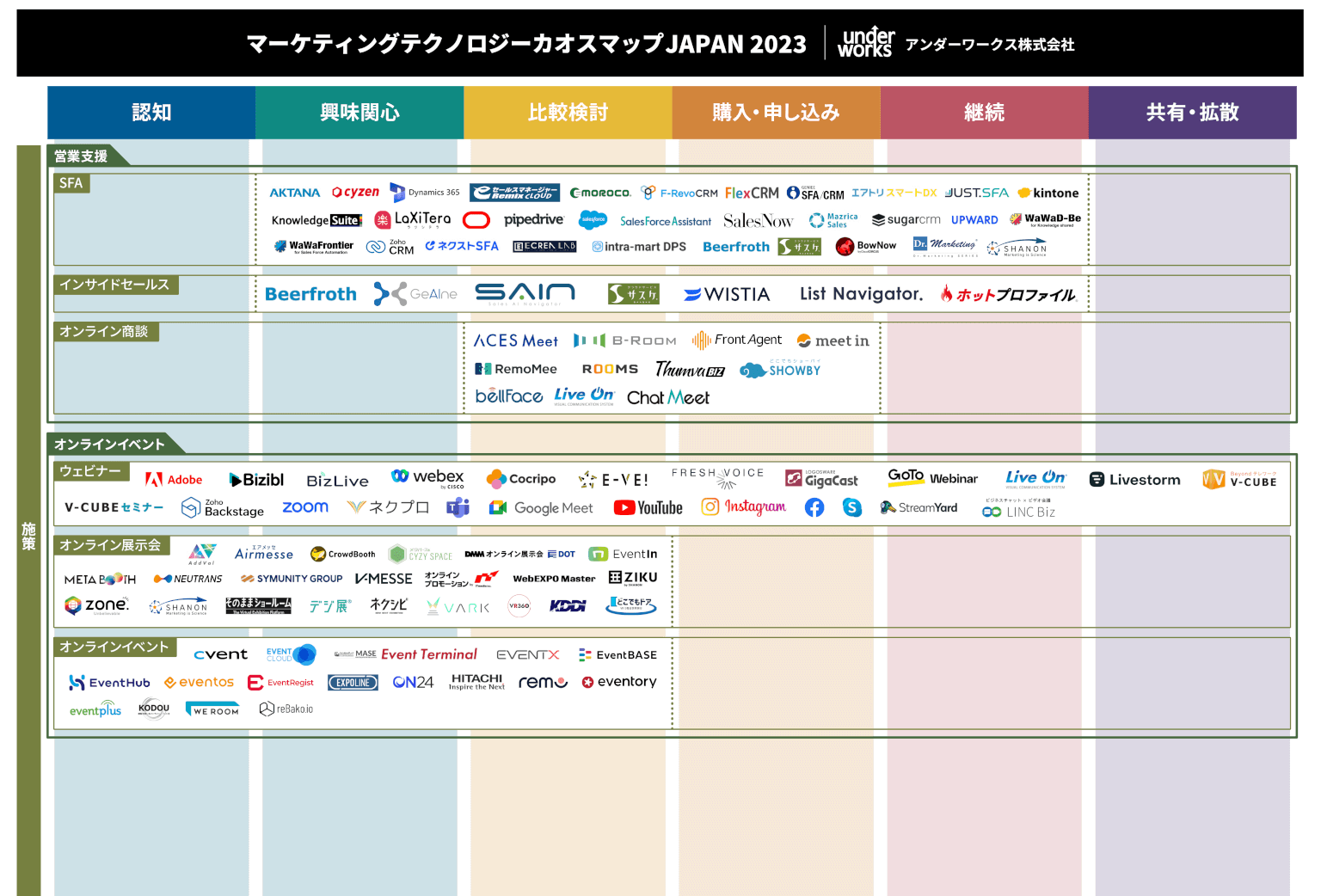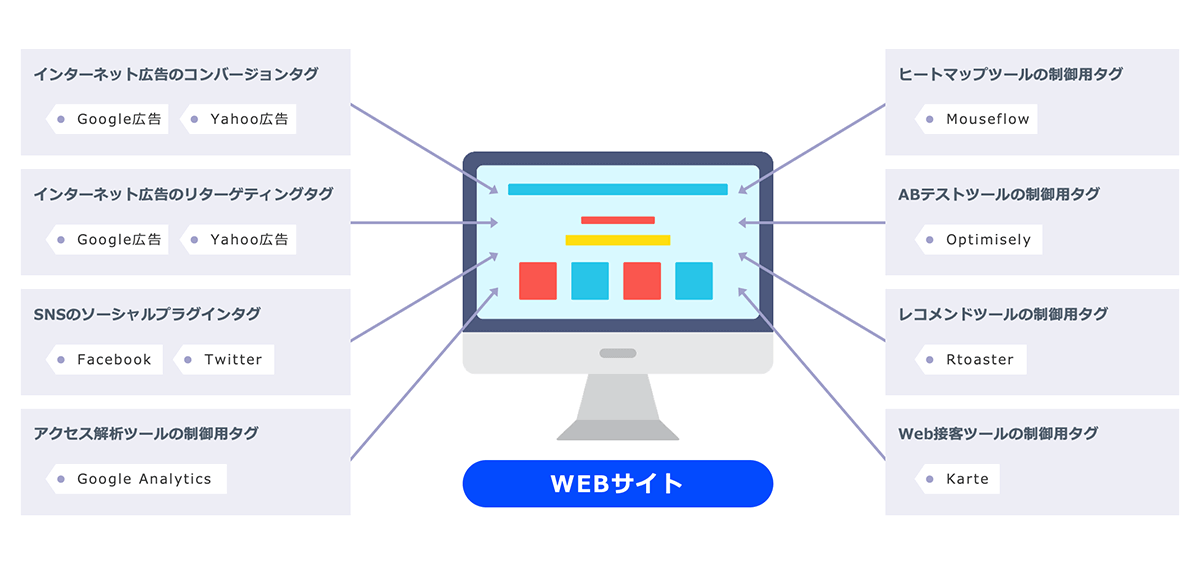コロナ禍でなかなか海外渡航が難しい状況にありましたが、日本の入国規制緩和を受け、海外出張や旅行の需要が再燃しています。今回は三年ぶりの渡米でラスベガス、ロサンゼルスのリテール企業を視察したアンダーワークス社外取締役/NODE代表取締役の金均氏に、現地のリテール企業・店舗のデジタル化がどういった視点で進んでいるのか、そこから感じたデジタルビジネスのこれからについてお話を伺いました。
(話:アンダーワークス株式会社 社外取締役/株式会社NODE 代表取締役 金均氏、聞き手:DMJ編集部)
※タイトル画像 RCP – stock.adobe.com
米国に見るリテール店舗のデジタル化を進める3つの視点
経営課題としてDXを議論する企業は皆無
今年9月に米・ラスベガスで開催された「Grocery SHOP」に参加し、その後ロサンゼルスにてリテール企業の新型店舗を視察した中で、米国ではDXは当たり前のことで、それを経営課題として議論する企業は皆無だと感じました。
視察したほとんどの店舗ではECの在庫データと店舗の商品・顧客データの連携が完了しており、アプリで商品バーコードを読み込んで注文できるだけではなく、たとえばウォルマートでは商品情報やユーザーレビューなどが表示されたり、アパレル店舗だとブランドストーリーが表示されたりもします。セルフレジやカーブサイドピックアップに至ってはほぼ全ての店舗に設置してあるほど当たり前に導入されていました。
では、どこの店舗も当たり前にデジタル化を進める中で、一体何をもって他社と差別化するのでしょうか?それは「サステナブル」「エンターテインメント」「ウェルビーイング」の3つの視点で創られる顧客体験です。
まず、ダイバーシティの概念が日本とは全然異なると感じます。アパレル企業のポスターでは国籍だけではなく多様な体型・髪型の人を映した写真でダイバーシティを感じさせるものが多く見られます。単に店舗の利便性を高めるだけでは勝負にならないので、TikTokやライブコマースによって顧客体験を面白くしていくことで差別化する傾向も顕著です。企業のDXというよりも、世の中に新しい価値観をどう浸透させていくか、それによって本当に魅力的な顧客体験をつくれるかの戦いになっているんです。
「ウォルマート変革」で押さえるリテール店舗の歩み

アメリカにて店舗のデジタル活用が進んだ背景には、世界最大のスーパーマーケットチェーンである「ウォルマート(Walmart)」の変革が大きく関わっています。2014年にダグ・マクミロン氏が社長に就任してから同社はテック企業として大きく成長し、デジタル関連投資額が設備投資総額の5割に達するほどになりました。比例して売上も伸び、2019年には米・Amazonよりもアプリユーザーを増やすことにも成功しています。
ウォルマートはリアル店舗を有する強みをもって、徹底的に店舗を活かしたOMO体験を実現しました。2015年からは、BOPISと呼ばれるオンラインで購入して店舗で受け取りができるサービスを中心にデジタル化を進め、車で受け取れるカーブサイドピックアップを普及させるなど継続的に仕組みを開発し、拡大し続けてきました。
さらにアプリの使い勝手を向上させ、ECと店頭体験を連動・統合したアプリ体験を提供できるように大きく変革したことで、1年で米国世帯数の約4割が有料メンバーになるなどユーザー数と売上の増加を推し進めています。
ロサンゼルスの最新リテール店舗体験
ウォルマートの他にも、金氏がLAで訪れた店舗の多様なデジタル活用をいくつか紹介します。百貨店チェーンである「メイシーズ(Macy’s)」でもカーブサイドピックアップが導入されている他、オンラインで注文した衣類を店舗で受け取り、フィッティングルームで試着した上で不要であれば「リターンボックス」に簡単に返品ができ、返金されるようになっています。コロナ禍で定着したというリターンボックスですが、これを使った来店客は、せっかくなので店舗で買い物をしようと多くが店内に向かうといいます。

2017年に米・Amazonに買収されたスーパーマーケットチェーンの「ホールフーズ(Whole Foods Market)」が、Amazonの会計テクノロジーを導入した「Whole Foods with Just Walk Out」にも注目です。入店時にAmazon IDでチェックインし購入するものを持ってゲートを出ると自動的に集計・精算される、いわゆる「Amazon Go」のシステムですが、驚くのは複数人で入店するとグループと認識され、最後の集計時にもグループ精算になる点です。

大型スーパーマーケットの「ターゲット(Target)」は独自のD2Cブランドを次々と開発し、現在では49ものPB(プライベートブランド)が誕生しています。メンズ向けの「Goodfellow & Co」やアクティブウェアの「JoyLab」など、食料品だけではなくファッション、コスメジャンルでも多様なユーザーに向けたPBが展開されており、どれも新たなブランドのように見せているのが特徴です。これらのブランドが店舗でも大きく棚を取っており、ターゲットの5兆円の売上の内約3割がPBの商品売上であるなど、デジタル化とは異なる観点ですが、独自のブランド商品を求めて顧客が来店するような集客の成功例として注目です。

さらに店舗のローカル化として、全米有数の高級百貨店「ノードストローム(Nordstrom)が、都心近郊や小さな街に「Nordstrom Local」といった小規模店舗を設置しています。ここではオンライン注文の受け取り、試着、衣類のお直し、返品ボックスといったサービスが利用できるなど、巨大店舗を地方につくらずともECで見つけた商品と直接触れ合うポイントを各地に設けています。
ローカル店は都心ほど来店客数が多くはないため、店舗で働く店員はノードストローム社の社員であることも面白い点です。マーチャンダイザーやスタイリストなどの社員が、普段はバックヤードやカウンターデスクで業務をしながら顧客が来店した際には直接接客をするなど、人材効率の高い手法でローカル店舗を運営しています。


Amazon Styleに見るデジタルと店舗を融合させた体験
一方、もともとデジタルを主戦場としていた企業による店舗の利活用にも多様な取り組みが見られます。2022年5月にできたAmazon初のアパレル実店舗「アマゾンスタイル(Amazon Style)」では、約840坪の広大な面積フロアの中でデジタル技術と店舗が融合した新たな購買体験を可能にしています。
入店時にAmazonアプリでチェックインし、気になった商品をQRコードで読み取ると、レビューや価格、店舗在庫がチェックできるようになっています。陳列される商品は全て「見る」ためのサンプルであり、実際に試したい商品があればアプリ上の操作で試着室に送ることができます。アプリ上では「今日の買い物へのお薦め商品」も表示され、イメージ画像への好き・嫌いの回答から分析されたお薦め商品が試着室に運ばれるようになっています。

10分ほどすると試着室の準備完了がアプリで通知され、同じくアプリで解錠すると、先ほど選んだ商品とAmazonから自分へのお薦め商品が陳列されているんです。試着室内のタッチスクリーンに希望のサイズなどを入力すると、試着室と繋がっている扉から追加のオーダー品を受け取ることができるなど、効率化・パーソナライズされた一人ひとりの購買体験がつくられています。アプリやスクリーン、ECや店舗データなど色々なデジタル技術が一つの店舗に集まり、それらが連動して新たな購買体験を生むところまで米国は進んでいると感じました。

メーカーは「バズ」と「パーパス」で勝負を
小売企業だけではなく、既存のメーカーブランドも各自の取り組みを展開する様子が見られました。普通に商品を生産するだけでは売れないので、「バズ」と「パーパス」で勝負していく傾向があるように感じます。たとえば「alo」というヨガファッションブランドは精神性を大事にするパーパスを持ち、ほとんどの売上はオンラインでつくりながらもメッセージを伝える場として店舗を捉え、小ロットで頻繁に新製品を出して訪問したくなる店舗づくりに注力しています。
インクルージョンやサステナビリティを推進する下着ブランド「Parade」では、多様な体型や肌の色の人たちが共に幸せに美しく着用できる下着を目指し、ビジュアル面でも多様性の形を表現しています。さらに、古着やリユース品がサステナブルの観点で注目され、ノードストロームやメイシーズなどの百貨店でもおしゃれに陳列・販売されるなどの動きも見られました。

本質的・魅力的な顧客体験をつくるリテール業界へ
今回の渡米でわかったことを端的に言うと、アメリカのリテール企業は本気だということです。ECがどう、アプリがどうといった手段の話ではなく、小売業そのものの業態変革を全社が牽引し、店舗とデジタルを融合した顧客体験の提供を推し進めています。コンサルタントやIT企業に頼むのではなく、自分たちで何とかしないといけないと、組織変革を含めインハウスに向かっていく動きがあります。
日本企業がキャズムを超えられなかった背景としては、既存業態は温存しながら部門別や個別領域でDXを進めたため、本質的な業態変革に踏み込めなかったことが収益性の差になっているといった点があります。一方で、来年から米国リテールの視察に赴く企業が増え、このままではまずいと気が付きそこから国内企業も動いていくでしょう。小売業は経営者が全社でインハウス化していき、デジタルと店舗を融合させ魅力的な顧客体験の創造に注力していく動向になっていくと、期待も込めて予測しています。
この記事をご覧になった方も、コロナ禍で米国のリテール企業がどのような変革を行ってきたのか、身を持って体感し本質的・魅力的な顧客体験とは何かを考える機会になりますので、ぜひ今のタイミングで渡米することをお勧めします。